
いわさきちひろ 黄色い傘の少女 1969年
いわさきちひろは、大胆に余白を取った画面に、たっぷりと水分を含んだ筆で四季折々の子どもの姿をとらえました。雨のにおいや、空想を広げてひとり遊びをしていた記憶……。その絵は、見る人の胸の内に、さまざまな情感を喚起します。
本展では、作品の背景にあるちひろの感性の源泉を探り、その詩情あふれる絵の魅力に迫ります。

いわさきちひろ 朝顔と三人の子どもたち 1970年頃
ちひろが愛した詩
ちひろが娘時代に親しんでいた文学のひとつに「万葉集」があります。昭和13年に出版された斎藤茂吉の『万葉秀歌』をきっかけに、ちひろはいくつかの歌を暗唱するほど万葉集の世界に夢中になったといいます。愛する人への想いを歌に託した万葉歌人の人間性や、万葉の昔から変わらぬ子どもの愛らしさを墨と鉛筆で巧みにとらえて表現しています(図2)。

いわさきちひろ 常陸娘子(ひたちのおとめ)『万葉のうた』(童心社)より 1970年
また、同じくちひろが娘時代から親しんでいたのが、宮沢賢治の作品です。賢治の作品と出会ったころのことを次のように語っています。「私の娘時代はずっと戦争のなかでした。女学校をでたばかりのころは、それでもまだ絵も描けたし、やさしい美しい色彩がまわりに残っていて、息のつけないような苦しさはなかったのですけれど、それが日一日と暗い、おそろしい世の中に変わっていきました。そんなころに私ははじめて宮沢賢治の作品にふれたのです。」ちひろの賢治への傾倒は終戦直後に頂点に達します。終戦の翌日から書き始めた日記のなかには次のように記されています。「きのうから宮沢賢治の事で夢ごこちだ。(略)いまは熱病のようになってしまった。前に詩集をよんだ時もっともっとよく読んでおけばよかった。」ちひろが宮沢賢治の作品を描いたのは、童画家となって20年ほど経てからのことです。1969年、ちひろは50歳のときに、花や植物を題材に書いた賢治の童話を集めた『花の童話集』に取り組みます。賢治の物語のなかで擬人化されている樹木や草花を、ちひろは、まずスケッチをして自然に近いかたちで描きました。賢治の文章をそのまま説明するのではなく、賢治の自然を見つめるまなざしに共感し、文章から感じた印象を絵で展開させています。

いわさきちひろ ひなげし『花の童話集』(童心社)1969年
ちひろの詩
はなやさんの まどは
はなやさんの
まどは
くもっている
それで
わたしは じを かくの
きれいで
やさしい
はなのじなのよ
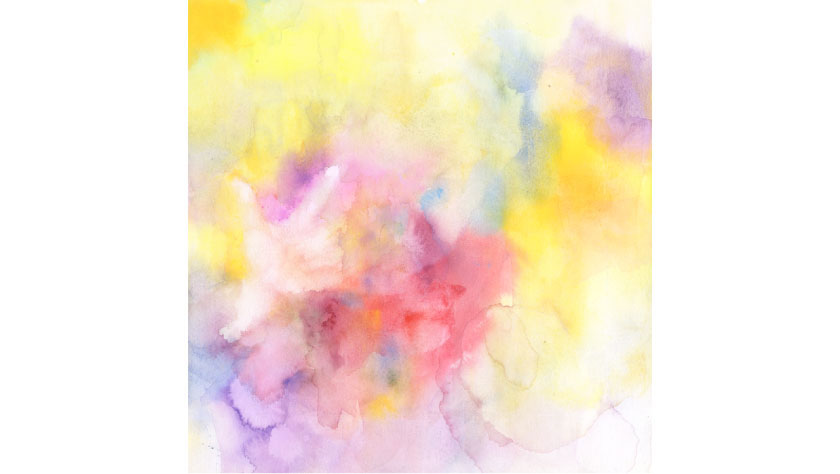
いわさきちひろ 「はなやさんのまど」1969年
この詩は、1970年に絵雑誌「こどものせかい」に絵とともに掲載されたちひろの詩です。ちひろは、雑誌や新聞などで、絵とともに詩を発表しました。やさしいことばと絵の組み合わせには、ちひろの幼いころの感覚や好奇心がみずみずしく映し出されています。こうした子どもの心と響き合う感性は絵本のなかにも生かされています。
感じる絵本
ちひろは、1968年に至光社の編集者・武市八十雄氏とともに「絵本でなければできないことをしよう」と実験的な絵本づくりに取り組みます。子どもの感受性をテーマにした絵本シリーズは、「感じる絵本」と呼ばれ、当時の主流であった物語絵本とは異なる、新しい絵本の可能性を開きました。4作目にあたる『ことりのくるひ』では、場面ごとにタッチや、視点、色調などを変えて、「小鳥がほしい」という気持ちが芽生えた少女の心の動きを映し出しています。余白を生かした、やわらかな水彩の表現により、小さな命と心を通わせようとする少女の内面がいきいきと描かれています。

いわさきちひろ 小鳥と少女『ことりのくるひ』(至光社)より 1971年
ちひろは、この絵本シリーズで、最初に手がかりとなる「小鳥がほしい」といったイメージを膨らませて、そこから余分な要素を削っていくつくり方をしています。
このころ、ちひろは、自らの絵本づくりを、短いことばで心情を豊かに伝える俳句の手法にもなぞらえていました。こうした表現を模索するなかで、ちひろは、世阿弥が著した芸術論『風姿花伝』にも共感し、画用紙の端に「惜(せき)墨(ぼく)」「捨(すて)技(わざ)」ということばを書き写しています。“業(わざ)を捨(す)て”、“墨(すみ)を惜(お)しむ”という言葉は、ちひろの“引き算”の考え方をあらわしています。
あえて描かないことで、より深く、想像が広がる表現を目指していたことがわかります。
<定例のイベント>
松本猛ギャラリートーク
ちひろの息子である松本猛が、作品にまつわるエピソードなどをお話しします。
○日 時:9月3日(日)14:00~
○講 師:松本猛(絵本学会会長・ちひろ美術館常任顧問)
○参加自由、無料
ギャラリートーク
毎月第1・3土曜日 14:00~
会期中の開催日:9/2、9/16、10/7、10/21、11/4










SNS Menu