
ユゼフ・ヴィルコン 『地球の4人の息子たち』より 1991年
ポーランドとフィンランドとの国交100周年を記念し、ちひろ美術館コレクションから、両国の画家たちの作品を紹介します。
フィンランドは1917年、ポーランドは1918年にそれまでの列強による支配の後、独立を勝ち取ります。国家を持てなかった歴史のためか、2国はそれぞれ自国のアイデンティティーを大切にするようになりました。暗く長い冬の間の読書は大切な文化のひとつとして尊ばれ、多彩な絵本画家たちが活躍しています。
ポーランドの代表的絵本画家ともいえるユゼフ・ヴィルコンは、時代によって画風を果敢に変えてきました。当館にある130点近い作品のなかでも最も古いもののひとつが、絵本『あるクジャクの冒険』です。

ユゼフ・ヴィルコン(ポーランド)『あるクジャクの冒険』より 1960年
表紙絵には、クジャクの羽が細いペンの線と絵の具のにじみなどで巧みに表現されています。第二次世界大戦後の欧米の美術界で起こった、絵の具を垂らし、飛散させる抽象絵画に感化され、彼はそれを小さい紙の上で試みたといいます。1970年代以降のパステルの作品では、鮮やかな色とやわらかいタッチが目をひきます。

ユゼフ・ヴィルコン(ポーランド) 『地球の4 人の息子たち』より 1982年
エルジュビェタ・ガウダシンスカの作品では、なめらかな曲線でデフォルメされた人物の背後に、古典絵画を思わせる静謐な遠景が広がっています。絵のなかの人物は俳優だと語る彼女の絵は、読者を絵本という劇場へ誘います。

エルジュビェタ・ガウダシンスカ(ポーランド) 『マルチンとおそろしいどろぼう』より 1987年
ちひろ美術館コレクションには3 人のフィンランドの画家の作品が所蔵されており、いずれも1980年代に出版された絵本のための作品です。研究者のマリア・ラウッカは、80年代のフィンランドの絵本イラストレーションについて、特に発展のめざましい時期であり、非常に多数の読者を得た力強い芸術表現となった、と評しています。※
ペッカ・ヴォリの描くフィンランドの昔話の巨人たちには、余白のある大胆な構図のなかに、彼らしいユーモアが見てとれます。コラージュされた黒い紙の上に白の細かい線を重ねたハッチングの技法で、大地を表情豊かに表現しています。

ペッカ・ヴォリ(フィンランド) 『巨人のはなし』より 1981年
カーリナ・カイラは、アンデルセンの物語を、透明感のある水彩絵の具で物憂げに表しています。細部まで描きこんだ絵からは、落ち葉の音までが聞こえてくるようです。

カーリナ・カイラ(フィンランド) 『おやゆびひめ』より 1988年
※ Maria Laukka, “Finnish Illustrators of Children’s Literature”, in MIELIKUVIA, 1989
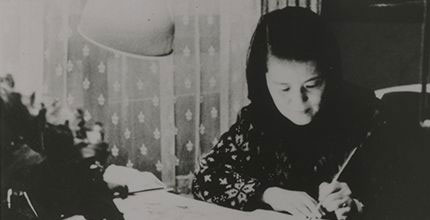




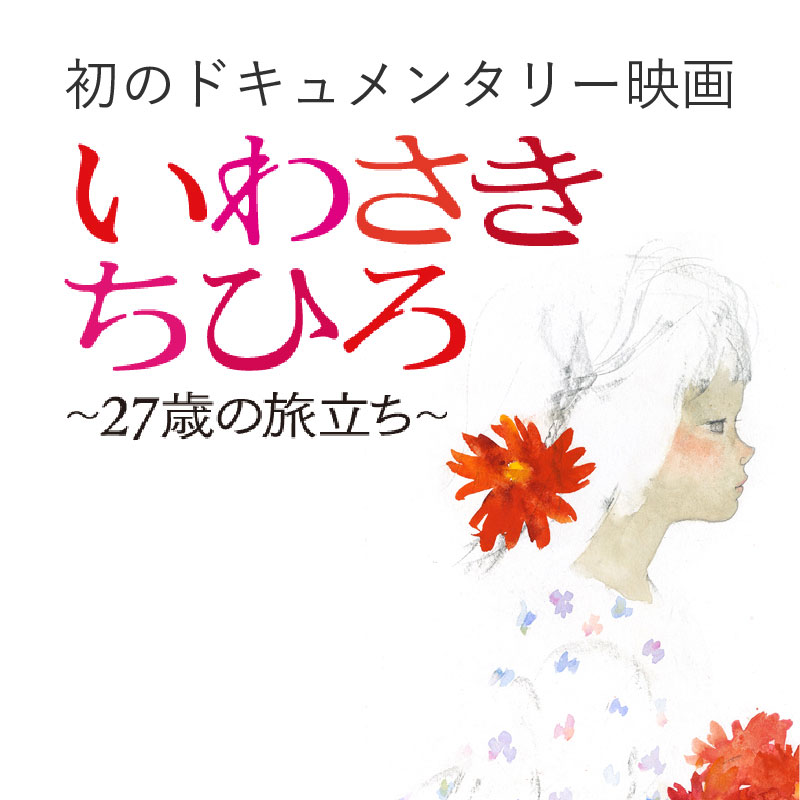


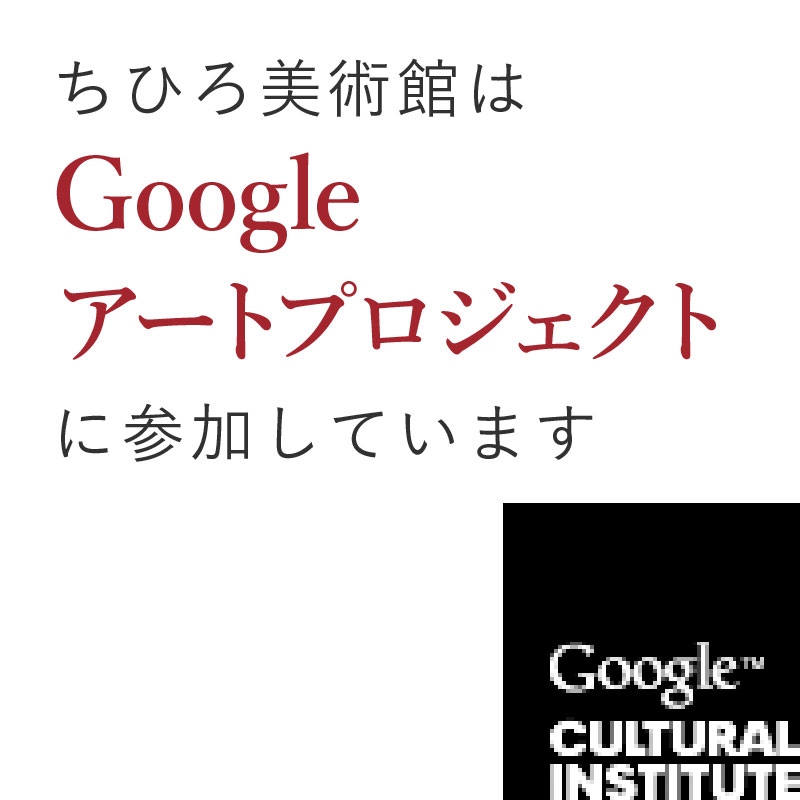


SNS Menu